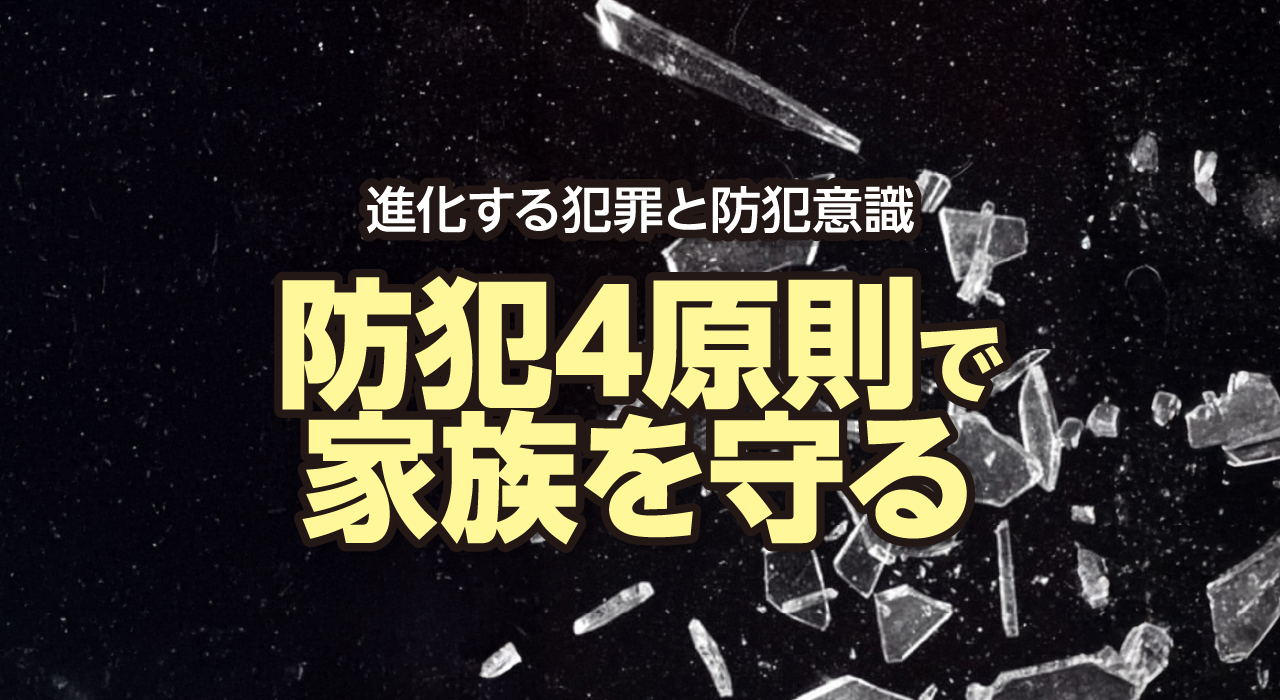通称「とくりゅう」と呼ばれる、匿名流動型犯罪グループが引き起こす特殊詐欺や闇バイト強盗事件。これは、昭和や平成の時代には見られなかった新しいタイプの犯罪です。
かつての窃盗と現在の手口
かつての窃盗は、「空き巣」や「居抜き」「忍び込み」など、住人と接触しない、もしくは接触しても盗むことを目的としたものでした。
「空き巣」は住人の不在を狙い、家人と接触せず財産を盗むもの。「居抜き」は住人が洗濯や食事、入浴中に家屋に侵入し窃盗するもの。「忍び込み」は住人が就寝中に忍び込んで窃盗します。
現在では、手口もさらに巧妙化しています。「ピッキング」は、玄関ドアを鍵以外の道具で開ける方法で、熟練のプロによっておこなわれます。「三角割り」は、マイナスドライバーを窓枠とガラスの間に入れて割り、音もなく解錠し侵入する手口。「焼き割り」は、ガラスをバーナーで熱して割り、やはり音もなく侵入します。
また、昔ながらの泥棒は「抜き足、差し足、忍び足」で、爪先を静かに抜くように足を上げ、そっと爪先から着地させて歩く、非常に慎重な動きをしていました。
在宅中を狙う凶悪化する犯行
しかし、現在では「とくりゅう」をはじめとした匿名流動型犯罪グループによる、住人が在宅中に侵入し金品のありかを聞き出して強奪するような犯行も報じられています。他の犯罪グループでも同様の手口が使われることがあり、財産だけでなく命まで奪われかねません。
狙われる家の特徴
犯罪者側の視点に立てば、どのような家が狙われやすいかが見えてきます。彼らは、短時間で確実に多額の金品を奪うことを目的としており、そのために事前の情報収集を欠かしません。電話での架空アンケート調査や、訪問販売、宅配業者、リフォーム業者などを装って、在宅時間や家族構成を把握し、ターゲットかどうかを選定します。場合によっては、住人自身がSNSで高級な車や食事、買い物などの情報を発信していることもあります。それが資産家であること、不在時間、在宅時間を示す手がかりとなっているのです。
彼らにとって、金品のない家に侵入し、何も得られずに終わることは避けたいところです。さらに、グループで役割分担して動くため、車移動が基本です。細い道路や行き止まりは作業しづらく、植栽で外から見えない家や近隣が少ない家は、犯行しやすい環境といえます。高齢者や独り住まいの方は、抵抗が少なく、狙われやすい傾向にあります。
一方で、狙いにくい家もあります。分譲地のように住民以外が入りにくいエリアであり、近隣の目が多い場所。防犯設備が設置されている家。侵入しにくく、逃げにくい環境は、犯罪者にとって避けたい条件なのです。
防犯4原則と備えの大切さ
これから住宅を検討する方は、防犯の視点を取り入れて選ぶことができます。しかし、現在の住まいで近隣環境を変えることはできません。その場合は、「時間」「目」「音」「光」という防犯4原則を参考に、自宅に取り入れていくことが有効です。これらは、それぞれ「侵入までに時間がかかる」「人目につく」「音が出る」「明るい」といった、犯罪者が嫌う環境をつくるための基本的な対策とされています。具体的には、補助錠を設置して解錠に時間をかけさせる、防犯カメラやセンサーライトを設置して周囲の目を意識させる、踏むと音が出る砂利を敷くなどの方法が挙げられます。
犯罪は災害の一つと捉え、防災と同じように備えることが求められます。防災力と防犯力を高めることが、家族と家計を守ることにつながります。