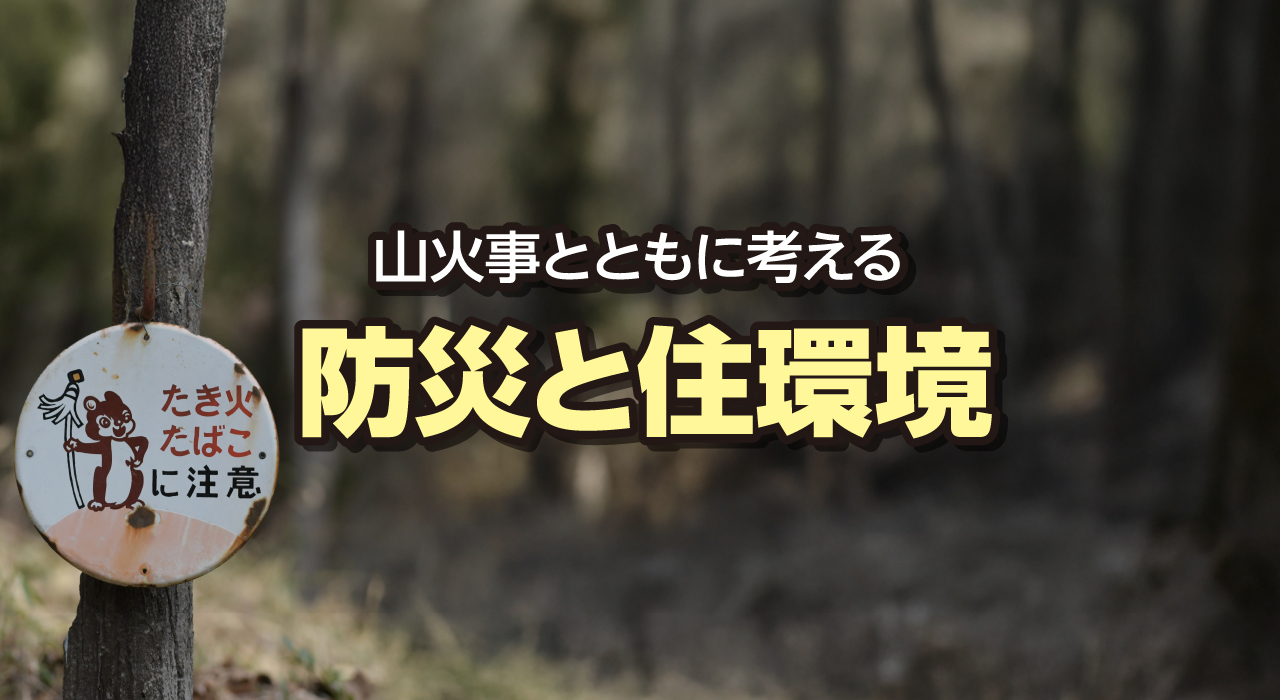ロサンゼルス、そして日本国内では大船渡、長野、奈良、岡山、今治、宮崎、さらには韓国でも山火事による広範囲な被害や避難指示のニュースが相次いでいます。出火原因は特定しづらいケースが多いようです。
春は山火事が多く、特に4月と3月に集中し、年間で1,000件を超えると言われています。これは、山に入る人が増えたり、農作業に伴う下草を焼く「火入れ」が行われるためです。
もし、たばこの投げ捨てや焚火が原因であれば、不注意にもほどがあります。山と海に囲まれた日本では、山火事が発生すると逃げ場を失う危険性が高くなります。動物たちもすみかを奪われ、焼けた山林が元に戻るまで食べ物が得られないため、人里に降りてこざるを得なくなります。
消えない火種「ゾンビ火災」
火災に関する言葉の使い方も難しいものです。「鎮圧」とは、目に見える炎がなくなった状態であり、「鎮火」とは異なります。完全消火の難しさは、地中でくすぶり続ける「地中火」によって再び燃え上がる可能性があることからも分かります。いわゆる「ゾンビ火災」です。サーモカメラで高温部分を確認し、熱源が残っている場合は掘り起こして消火します。内部の温度が高い樹木はチェーンソーなどで伐採し、消火する必要があります。足場の悪い斜面では、人海戦術で確認するしかないようです。
日常生活での火災リスク
風が強く乾燥する時期には、火を使わないこと、火元をつくらないことが大切です。燃えやすい枯れ草や立ち木だけでなく、民家も火災の燃料になります。木造住宅が密集する地域では延焼の危険が高く、まるで山林火災のように被害が拡大することがあります。
火を使わない暮らしへ
これからは、火を使わない生活を検討すべき時代かもしれません。調理器具について、環境省の調査(2023年3月)によると、IHクッキングヒーターの普及率は25.9%(戸建て住宅33.4%、集合住宅17.0%)と、約4軒に1軒の割合です。高齢化が進む日本では、80代のほぼ全員が白内障になると言われています。ガスコンロの火が見えなくなることは、大変危険です。
また、給湯器については、エコキュートの普及率が戸建て住宅で26%、集合住宅で3.2%とされています。光熱費が高騰する時代において普及が進んでおり、電気使用量は増えるかもしれませんが、お湯をつくるランニングコストは、ガスや石油の給湯器に比べて大幅に安いことが理由です。さらに、火を使わない仕組みのため、ガス漏れや火災の心配がないという安全性も評価されています。
防災につながる住環境づくり
住環境の整備も重要です。空き家が増えることは、放火などのリスクを高めます。自宅が火元にならないよう注意することはもちろん、近隣から出火する可能性も考えなければなりません。防ぎようがない場合もありますが、分譲地では耐火性能の高い新築住宅が立ち並び、全戸が電化住宅であれば、防災に強い街並みとなります。同じ年代の住民が多いことも、防災意識の高さにつながるでしょう。私たち一人ひとりが、住まいや設備の安全性を見直し、小さな対策を積み重ねることが、火災リスクを減らす第一歩になるのではないでしょうか。