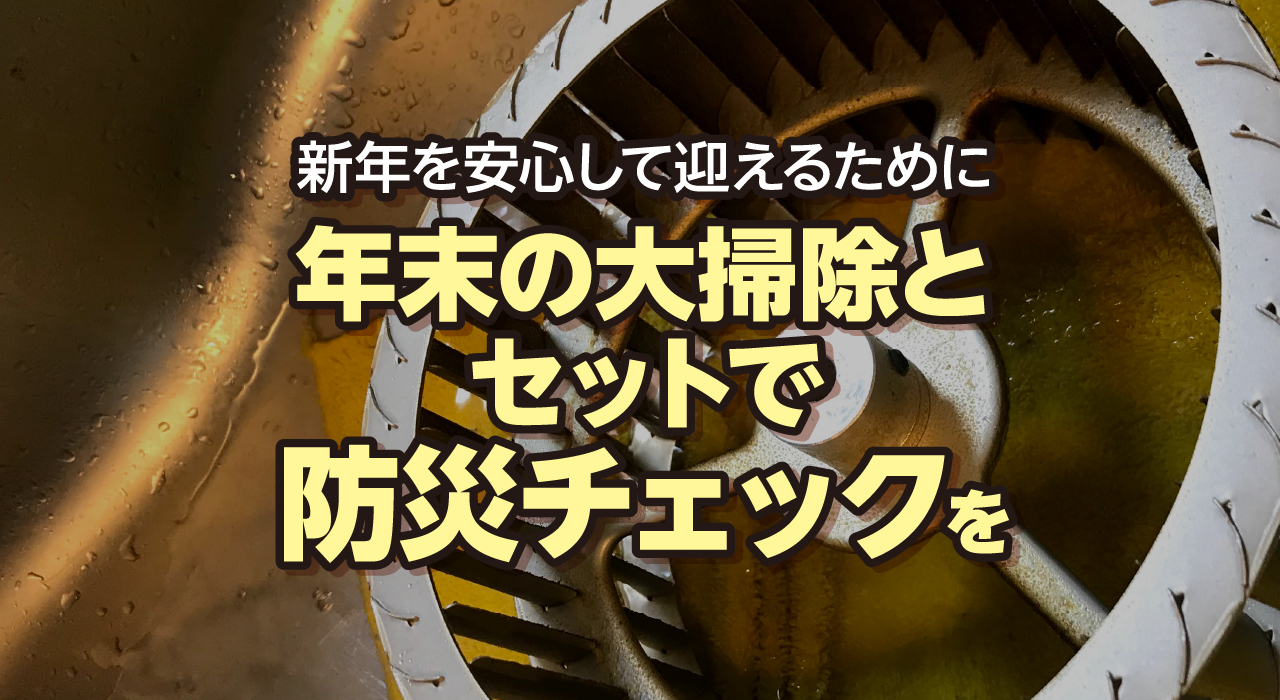1年が経つのはあっという間と感じるのは、年齢を重ねたからでしょうか。乾燥するこの時期、乾いた咳が特徴のマイコプラズマ肺炎の広がりが心配です。コロナウイルスとの同時感染が懸念される中、年末の忙しさをさらに増やさないためにも、マスクの着用や手指消毒を改めて徹底することが重要です。冷たい水で手を洗うのが億劫に感じることもあるかもしれませんが、感染予防の基本を守りましょう。
年末の大掃除とセットで、防災や防犯を意識して、住まい見直してみてはいかが?
窓ふきや網戸の交換、換気扇掃除など、寒さの中での大掃除は暖かい格好で行いましょう。その際、防災や防犯を意識して、住まい見直してみてはいかがでしょうか。
能登の地震から1年が経とうとしています。災害はいつ起こるかわかりません。
大掃除の際に、耐震補強金物や家具転倒防止器具の設置を検討しましょう。家具の転倒による圧死や大けがを防ぐためです。
また、食器戸棚から揺れで落ちた皿やコップが割れると足を負傷する恐れがあります。耐震ラッチなどで扉が開かない工夫をすることも大切です。家の中の危険箇所を確認しながら掃除をおこなうことが防災対策につながります。
庭掃除の際は、植木鉢やプランターが強風で飛ばされないよう工夫することで、竜巻や台風対策になります。また、使用した脚立やはしごを放置しないことも重要です。侵入に利用される可能性があるため、防犯のためにも後片付けをしっかりおこないましょう。
窓周りの掃除では、補助鍵を設置して窓からの侵入を防ぐとともに、小さなお子さまの転落やペットの脱走防止にも役立ちます。窓の鍵(クレセント)が緩んでいる場合、簡単に外れてしまうことがあるため注意が必要です。チェックを忘れずに。
室内では、火災警報器の動作確認を忘れずにおこないましょう。電池切れでは警報が鳴らず、意味をなさなくなります。特殊な電池を使用しているタイプもありますので、10年以上経過しているなら本体そのものの交換を検討しましょう。単独型の警報器はその部屋のみで警報音が鳴る仕組みですが、連動型に替えることで、火元以外の部屋でも警報が鳴り、逃げ遅れを防ぐことができます。
火災警報器は階段や寝室に設置が義務付けられていますが、罰則がありません。気になる場合はこの機会に設置を検討してみてはいかがでしょうか。
乾燥する時期は火の回りが早く、ボヤが大火事に発展しやすくなります。火災を防ぐためにも、火を扱う場所の大掃除が重要です。
汚れ防止用のフィルターは定期的に交換しないと、油を吸って目詰まりし、換気性能が落ちるだけでなく、火が付きやすくなります。
また、換気扇周辺にある電源の油汚れはトラッキング火災の原因にもなります。洗剤をスプレーする際には危険を伴いますので、慎重に掃除をおこないましょう。
防犯や防災の視点を持ちながら大掃除を進め、良いお年をお迎えください。今年もご購読いただきありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。